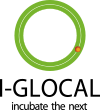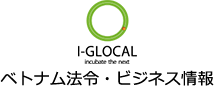業種別ベトナムM&Aの特徴・留意点 第5回~不動産業~
2025/03/14
- I-GLOCAL CO., LTD. ハノイ事務所
- 日本国公認会計士
- 近藤秀哉
はじめに
ベトナムは経済成長に伴う都市部の人口増加及びインフラの発展などにより、住宅物件の賃貸及び購買需要が年々上昇、住宅価格も右肩上がりの傾向にある。また外資企業の進出も盛んであり、オフィスビルの需要も高い。このためベトナム不動産は魅力的な投資先の1つであり、日本をはじめ韓国・シンガポール等の外資企業による、ベトナムでの住宅・オフィスビルおよび商業施設の開発を目的としたプロジェクト取得が盛んに行われている。
しかし土地使用権の取得に関する規制等、不動産業への進出をM&Aで行う上での留意点が存在する。本稿ではシリーズ第5回目として不動産業M&Aの留意点を解説する。
1. 外資規制および進出形態について
ベトナムでは100%外資企業が不動産事業を行うことも可能であり、外資企業が実施可能な不動産事業は以下のとおりである。
1) 住宅・建物のサブリース
2) 国から土地使用権のリース・割当を受けた土地での販売・賃貸向け不動産プロジェクト
3) 販売・賃貸向け不動産プロジェクトの全部または一部の譲り受け
4) 工業団地等での住宅・商業施設建設投資
5) 不動産仲介・取引・コンサルティング・管理サービス
一方で不動産事業は条件付き投資分野に該当するため、土地使用権の取得や事業内容は外資規制の影響を受ける。具体的には、上記に記載の無い、リース・転売目的での不動産の購入、企業や個人から土地使用権の譲渡・リース・転貸等は認められない。
上記の通り外資企業でも国から土地使用権の割当もしくはリースを受けての不動産開発が可能であるが、その際に各省庁へのヒアリングが必要になることから、他業種と比較して会社設立から事業開始までに時間を要し、難易度は比較的高いといえる。外資企業が単独で不動産開発を行う場合、建設開始まで約1.5~3年と長期間を要することが一般的である。
既存物件を取得して賃貸やメンテナンス収益を得るビジネスモデルもあるが、この場合でも土地使用権がネックとなり、好き勝手に物件を取得することはできない。このため一般的には以下のようなスキームが採用されることが多い。
① 不動産を保有しているローカル企業の株式・持分を外資が取得する
ローカル企業を通じて不動産開発や、当該ローカル企業が保有する土地建物を間接的に取得する方法であり、出資比率規制は無く100%出資も可能である。
出資したローカル企業の過去の負債・税務リスク等を引き継ぐため、出資前にDDをしっかり実施する必要があるが、新たに会社を設立する必要もなく手間がかからない方法である。出資対象会社が保有する土地使用権や環境許可、建設許可などのライセンス一式も引き継ぎ可能なため、多くの会社がこのスキームを採用している。ただし外資が買収した時点でこのローカル企業ステータスも外資に切り替わるため、買収後に新たな不動産を取得する事はできない(外資規制が適用される)点に留意されたい。
② 外資規制に抵触しないマイノリティ出資の合弁会社(JV)を地場パートナーと設立し、JVを通じて土地使用権等の不動産を取得する
現行の土地法31/2024/QH15では、投資法61/2020/QH14上に規定される外資企業に該当しない場合はローカル企業扱いになると定められている。投資法上の外資企業とは以下のいずれかの要件を満たす企業である。
1. 外資企業が定款資本金の50%超を有する合弁会社
2. 1の合弁会社が定款資本の50%超を有する合弁会社
3. 1の合弁会社と外資企業が定款資本の50%超を有する合弁会社
この要件を満たさないJVはローカル企業とみなされるため、土地使用権の取得等に関しても土地法上の外資規制の影響を受けない。ただし出資比率に応じた利益分配が必要になるため、当事者間の事前交渉が重要になる点に留意が必要である。また地場パートナーの財政状態等も重要になるため、地場パートナーに対してDDを実施することが一般的である。
本スキームは、上記①に記載した買収後に新たな不動産の取得ができないというデメリットを回避したい際や、外資規制に該当する事業を行う際に選択される場合がある。
③ 合弁会社(JV)を設立し土地使用権による現物出資を受ける方法
土地所有権を保有したローカルと合弁会社を設立し、地場パートナー企業からは現物出資を受ける形で希望の土地使用権を取得する方法である。この方法では、地場パートナー会社の持つ無期限の土地使用権を取得できることや、土地使用権のリース料の支払いが不要のため初期投資を抑えられるというメリットがある。取得したい土地使用権や賃貸事業用の既存物件を地場パートナーが保有しており、パートナーと共にプロジェクトを実施していく場合にはこの方法も一考に値する。
以下、最も一般的な方法である「①不動産をベトナムローカル企業が保有し、そのローカル企業の株式・持分を外資が取得する」パターンに焦点を当てて解説する。
2. 事業計画・投資回収スキームの留意点
M&Aを活用して土地所有権を取得する際、まずは土地所有権の期限に留意が必要である。特別なケースを除き土地使用権の期限は国より割当・賃借を受けた時点から50年である。土地法上は使用権の延長も認められうるとされているが、判断はベトナム政府に委ねられるため、延長不可の可能性も含めて事業計画・投資回収スキームを検討する必要がある。また、ベトナムは新興国であり特に都市部の土地や不動産相場の変動が激しいため、不動産や土地使用権の相場が短期間で変動し、投資回収期間が長引く可能性もある。
その他、住宅用不動産プロジェクトの場合、管轄の政府機関が土地法に従って購入者に土地使用権証明書(いわゆるピンクブック)が発行されるまでは95%以上の売買契約代金を受領できないという規定がある。土地使用権の目的等は通常DDの確認事項であるが、土地もしくはプロジェクト実施中に法令違反があった場合、ピンクブック発行が遅れ投資回収が遅れることもあるので留意が必要である。
なお不動産プロジェクトから発生した税引後利益は、他の業種と同様、配当による投資回収が可能である。
3. デューデリジェンス(DD)における主要なイシュー
不動産開発事業のDDにおいては、以下のような特有の論点が考えられる。
・登記・許認可の適法性
M&A対象会社が適法に環境・建設許可などの許認可を取得していない、または土地使用権証明書がないもしくは今後発行される見込みが乏しいにも関わらず不動産開発を進めようとしている、詐欺まがいの案件も散見される。
このため法務DDの際に登記・許認可の状況を慎重に確認することが最も重要である。また、外資規制を回避するために複雑な投資スキームが組まれていることもあり、投資スキームの適法性も合わせて慎重な検討が必要である。
・資金繰り・財政状態
不動産業の場合、開発資金を多額の出資もしくは借入金で手配することが一般的だが、出資の未履行や開発遅れ・長期化等により資金繰りに問題のある会社も存在する。DD では直近のキャッシュ残高および将来の資金繰り計画と、対象会社のビジネスモデルや不動産開発の進捗状況などを比較し、破綻の懸念が無いか慎重に検討する必要がある。
また、土地使用権に担保が付されているケースでは、開発には担保権者の承認が必要となることが多い。通常建設許可を得る際は担保権者の承認も確認されるが、仮に担保権者の承認を得ないまま開発を進めると後の売却や融資で問題が生じる可能性もあるため、DDで担保契約を確認する必要がある。
・当局等へのコミッション支払い
不動産開発を行うにあたっては投資登録、設計承認、環境影響評価、建設許可など多数の当局許認可が必要となる。これらの承認を得るには煩雑な書類準備が必要であり、また当局の審査が長引くこともある。そのため、便宜を図る目的で当局にコミッションを支払っているケースが散見される。これらの支払いは、費用計上せずに簿外処理されるケースや、CEOのポケットマネーから捻出されることもある。また、これらの各種許認可が、実体としては承認要件を満たしていないにもかかわらず、コミッションにて承認を得ている場合もある。
この場合、将来の査察で不備を指摘され、再度コミッションを要求されるリスクもあるため、許認可の有無を確認するのみならず、実態との整合も確認し、必要に応じて追加整備などを行わなければならない点に留意が必要である。
・テナントとの二重賃貸契約
その他、保有物件のメンテナンス・賃貸を行っている会社を買収する場合は、法人税を意図的に減らす目的で、本来の賃貸金額を記載した賃貸契約書とは別で、偽の低い賃貸金額を記載した賃貸契約書を合わせて作成し、2種類の契約書をテナントと締結していることがあるため留意が必要である。
おわりに
以上、ベトナム不動産業のM&Aにおける留意事項等の解説を行った。
不動産開発には多額の資金が投入され、外資規制も存在するため、投資スキーム・登記・許認可を中心にM&A時に確認すべきポイントが多岐に渡っている。その反面、一度スキームが出来上がってしまえば、M&A後のオペレーションはルーティンで回すことができ、ベトナムの経済成長を不動産収入という形で取り込むことが可能である。十分な知見を持った法務・税務アドバイザーとよく事前に相談し、不動産M&Aを進めていただきたい。